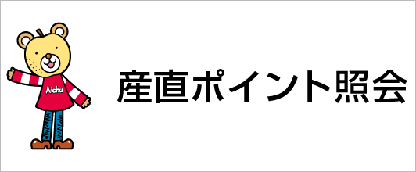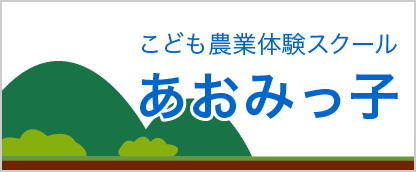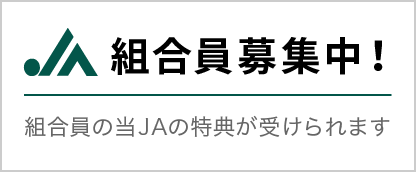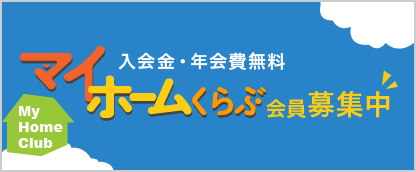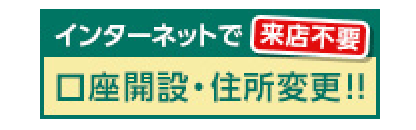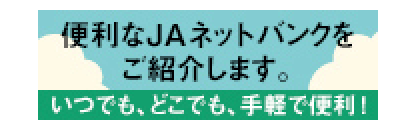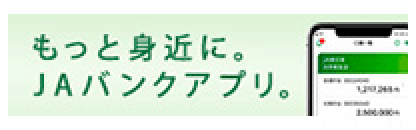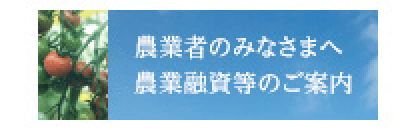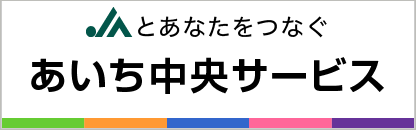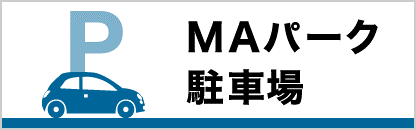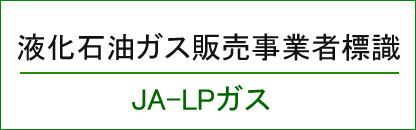トピックスレポート
防災意識日頃から 水田貯留で水害に備え ケーブルTVで発信
- 安城市立桜井中学校
2025/2/6
 生産者らが見守る中、カメラを前に発表するメンバー(右4人)
生産者らが見守る中、カメラを前に発表するメンバー(右4人)
安城市小川町の安城市立桜井中学校1年C組では、「総合的な学習」の授業で安城市の水害対策事業のひとつ「水田貯留」を学んできました。生徒は、2024年8月の「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を受けたことや同校が一級河川矢作川に近いことから水害への関心が高まり、水害に対する安城市の取り組みを調べていく中で、水田貯留事業を知りました。同市のホームページなどを調べたり、水田貯留事業に協力する水稲農家、JAあいち中央から聞き取りを行ったりして、知識を深めてきました。水田貯留を学ぶ中で、農地の多面的機能を知ると同時に農地が減っている現状を知り、どうしたら農地を守れるかを生徒それぞれの目的に合わせて9つのグループに分かれて考えてきました。
グループ「大呂みかこ」のメンバー4人は、多くの人に水田貯留を知ってもらうことで、同市の農業に関心をもってもらいたいとテレビで発信することを考えました。地元ケーブルテレビ(刈谷、安城、高浜、知立、碧南、西尾市)の株式会社キャッチネットワークに協力を呼びかけ、2月6日には同校で収録が行われました。学習をサポートした水稲農家とJA職員が見守るなか、緊張しながらもカメラに向かって堂々と学んだことなどを発表しました。
生徒は「一昨年、大雨で小学校前が浸水する水害を体験した。水害と水田貯留はつながっていると思った」「私たちが学ぶだけでなく、地域の人にも広めたいという想いが叶ってうれしい」などと話しました。
発表を見学した水稲農家の稲垣巨樹さんは「中学生が安城市の農業や水田貯留のことを調べてPRしてくれたことが、うれしい。周りの人にも伝え、今後もどう取り組んでいくと良いかを考え、実践してほしい」と話しました。
水田貯留とは、大雨や台風の時に、通常よりも5センチほど多く田んぼに雨水を貯めることで、排水路への急激な流入を軽減し、下流域の町を洪水や浸水から守る取り組みです。同市では、ハザードマップなどをもとに、水害防止に有効な田んぼを選定して計画的に取り組まれています。 この日撮影した様子は、19日に同社番組のKATCHTIME30内「地域の今」で放送される予定です。